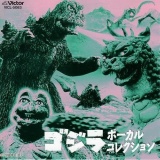2015年4月30日
丸投げ。
もう降らないのかなぁ...。
でも、まだ降るかもだしぃ...。
そうだ、おまえっ!(ビシィッ!)
代わりに見回りしてきたまえ。

2015年4月29日
ふくらんでます。
あ、あなたは...何ていう生き物なんですか?
「にゃー。」

2015年4月28日
あ、よいしょっ。
機敏ながら、胴回りの貫禄。
メタボですよ、おじさん。

2015年4月27日
二度目まして。
昨日はじめて出会ったにゃんこに再び遭遇。
少し打ち解けあえたような気がする春の午後。

2015年4月26日
はじめまして。
はじめてのおともだちと出会いました。
見つめず・立たず・近付かずで15~6分、
ようやく目を合わせて挨拶してくれました。
これからもっと仲良くなりたいものです~。

【てなもんやサウンド傘♪ 2015年4月26日19時半放送分】
旧盤の復刻専門レーベルというものが日本はもとより
世界中に存在しますが、復刻に際してのコンセプトは
様々で、例えば完全に忘れ去られていたような珍盤・
レア盤の発掘に熱心なレーベルもあれば、高音質の
追求に全力を注ぐレーベルもあるわけです。そして
今日ご用意しましたのは後者、独自のリマスターで
名盤たちに新たな命を吹き込もうと尽力している
アメリカのレーベル、Audio FidelityのCDです。
このレーベルはかつてDCCコンパクト・クラシックス
と名乗っており、現在は前述の通り名称を変更して
活動を続けています。復刻にあたっては、権利を保有
するレコード会社等と正式に契約を交わし、オリジナル
のマスターテープを借り受け、自分たちで独自に敏腕
エンジニアによるこだわりのリマスタリングを施して、
上位フォーマットのSACDにしたり、CDの素材として
24金を蒸着したり...と、徹底的な高音質化を図ります。
そんなAudio Fidelityによる最近の仕事の中で、特にうまく
いっていると思われる一枚が、Blood, Sweat & Tearsの
名作セカンドアルバム「Blood, Sweat & Tears」です。
アル・クーパーを中心に結成されたBlood, Sweat & Tears
は、ファーストアルバム発表後にアルを含め3人が脱退、
後任のヴォーカリストとしてデヴィッド・クレイトン・
トーマスが加入して1968年12月にリリースされたセカンドが
7週連続全米1位、グラミー賞4部門受賞という大成功を
収めました。
ロックとジャズを融合させ、ブラス・ロックという
スタイルを確立した彼らのサウンドを、Audio Fidelityは
よりブラスや各楽器のセパレーションを向上させ、
ヴォーカルのリアリティを高め、音像の奥行や立体感を
際立たせることに成功しています。そのことで、聴き手に
押し寄せるパワーはそのままに、それまでは渾然一体として
ひとつのカタマリのようであった音がハッとするほど整頓
され、ジャジーな側面の魅力を一層引き出しているのです。
演奏家の意図を正確に汲むこともリマスターの真髄である
一方、リマスターそのものもまた作品に新たな表現を付加
するクリエイティブな作業であるということを再認識する、
非常に印象的なリマスター盤でした。ちなみに本CDは
SACD/CDハイブリッド盤という仕様になっていますが、
従来のCDフォーマットにおいても手抜きのない音作りが
為されていることを付言しておきたいと思います。
(まさいよしなり)
「Blood, Sweat & Tears」/Blood, Sweat & Tears
[Audio Fidelity AFZ5-198 (米盤)]
オンエア曲:
1. Smiling Phases
2. You've Made Me So Very Happy
3. And When I Die
4. More And More
5. Spinning Wheel
Blood, Sweat & Tears/Blood, Sweat & Tears
2015年4月25日
恍惚。
おひさまを全身に浴びて...このお顔です。

2015年4月24日
連行。
おでかけにゃ、おでかけにゃ♪
どこいくにゃ、どこいくにゃ?
・・・びょーいん、いやにゃー(泣)

【我等音楽マサイ族 2015年4月24日放送分】
"犬の生活"のテーマ
/チャールズ・チャップリン(作曲[1959年])、
ミッシェル・ヴィラール・オーケストラ(演奏[1972年])
初期の映画には音声が付けられていなかったと
いうのはみなさんご存知の通りです。そういった
「サイレント(無声)映画」の時代から、いろいろな
試行錯誤をしながら音声ありの「トーキー」に
移行していったのが1920年代後半のこと。まず
アメリカでの導入が進み、次いで欧州へ。しかし
ここ日本では「活動弁士」という花型職業の存在も
あって、1930年代後半に至るまで「サイレント」と
「トーキー」がなお共存していました。
まさにその時代、世界的に活躍した喜劇王チャールズ・
チャップリン。自ら劇伴音楽の作曲まで手掛ける天才
でしたが、もちろんそれはフィルムに音声を記録
するようになった1931年の作品「街の灯」(ただし
この作品にセリフは一切収録されず、音楽のみ)以降
のことです。また、後年再編集版を制作したいくつかの
サイレント時代の作品にも劇伴が作曲されました。
こうしてチャップリンが遺した映画音楽の数々は
様々な演奏家や楽団によって録音され続け、今なお
楽しまれています。例えば元フィギュアスケート選手の
織田信成氏が現役時代にチャップリンメドレーを
プログラムに使いましたが、採用されたスタンリー・
ブラック指揮の録音も代表的な録音盤のひとつです。
さて今朝は、それらチャップリン作品の録音の中で
スタンダードとして認識されている、ミッシェル・
ヴィラール・オーケストラによる1972年のアルバム
から「"犬の生活"のテーマ」をお聴き頂きました。
この映画は1918年公開のサイレント作品なのですが、
1959年に再編集版が作られた際にチャップリン自身が
改めてこの映画のテーマとして書き下ろしたものです。
2015年4月23日
君と僕のぬくもり。
「おや、お目覚めいかがですか~?」と
あれこれ話し掛けておりましたところ、
奥からねぼけまなこのお方がもう一匹(笑)
いくら寝ても眠り足りないそうです。

2015年4月22日
伸びで始まる朝。
よしっ、がんばるぞぉぉぉぉぉ・・・!

2015年4月21日
こもれび、なでなで。
ごろごろ、うとうと。

2015年4月20日
店番の愚痴。
もう、こんな天気は飽きちゃったぁ。
おひさまに会いたいにゃぁぁぁ...。

2015年4月19日
基本、雨の日。
ずっと降ってるかと諦めてたけど、
しばらくやんでてホッとしたにゃ。
んっ、なんだかコケが湿ってるなぁ。
まぁいいか・・・むにゃ。

【てなもんやサウンド傘♪ 2015年4月19日19時半放送分】
スティーヴ・ガッドはニューヨーク州生まれのドラマー。
正確無比でありながらグルーヴ感を伴った彼のプレイは
評価も人気も極めて高く、そのスタイルに深く傾倒した
「ガッド・フリーク」なるフォロワー達を多く生み出した
超一流ドラム奏者で、広く敬愛を集めている存在です。
様々なアーティストとの幾多の名セッションについては
例を挙げ始めるとキリがないほどで、あえてカーリー・
サイモン、リッキー・リー・ジョーンズ、ポール・サイモン、
ジョー・コッカー、ポール・マッカートニー、スティーリー・
ダン、エリック・クラプトンといったところを列挙する
だけでも、いかに信頼されたドラマーであるか明らかです。
そんな彼ですが、実は今月(2015年4月)、70歳の誕生日を
迎えました。そして、そのバースデー記念としてこのたび
リリースされたのが、ニューアルバム「70 Strong」です。
リーダー作ともなれば、プレイも「前に前に」と主張して
いくものだという先入観がありますが、本作ではあくまで
トータルなサウンド構築に注力しているのがよく分かります。
メンバーひとりひとりを引き立たせ、バンドとしての魅力を
丁寧に磨き上げ、そして楽曲のクオリティを高めていく...
というスティーヴ・ガッドのコンセプトがはっきりと現れた、
極上のジャズ・フュージョン・アルバムに仕上がっています。
とはいえ、そこはもちろん彼のこと、涼しい顔で淡々と叩いて
いるようで、聴けばすごいプレイをやってのけています。
この「出来るが、出しゃばらない」という余裕が本当にニクい
限りで、カッコよさの極みです。70歳という大台を迎え、
なおパワーもセンスもますます冴え渡る全11曲の中から、
今夜は時間の許す限りピックアップしてお聴き頂きました。
まさにアルバムのタイトルのごとく「70にして強し」です。
「70 Strong」/Steve Gadd Band
[コロムビア COCB-54149]
オンエア曲:
1. Foam Home
2. The Long Way Home
3. Sly Boots
4. De Volta Ao Samba
5. Written in Stone
2015年4月18日
何かの予兆か。
にゃんこ直列。

2015年4月17日
この表情。
いくら春って言ってもさぁ・・・、
笑ってばかりもいられねぇよなぁ。

【我等音楽マサイ族 2015年4月17日放送分】
ゴジラさん/青木はるみ [1955年]
ゴジラといえば、みなさんご存知の「大怪獣」。
1954年11月に第1作が公開され、その後国内
のみならずハリウッドにおいても新作が続々と
生まれ続けているという世界的な存在です。
国内において更なる最新作が製作されるという
ニュースが先般報じられ、話題となったところです。
さて、こういった話題作が世に出ると、決まって
それにあやかった「便乗作」が作られるというのも
歌謡曲の世界でよくあることでした。そこで今日
ご用意しましたのは、初めて作られたゴジラ・ソング
と言われている1955年リリースの「ゴジラさん」。
歌っているのは芸者スタイルでデビューした
青木はるみで、1954年の「野球けん」の大ヒットで
知られています。(ちなみに、この方のお兄様は
「柿の木坂の家」を大ヒットさせた青木洸一)
もちろんこの「ゴジラさん」は映画の中にも使われて
いませんし、イメージソングでもありません。しかし、
「ゴジラ・ソング1作目」としてゴジラ関係のCDに
収録される機会も多いため、ファンには有名です。
2015年4月16日
心配をよそに。
え? 落ちませんよ?
...落ちませんってば。

2015年4月15日
最後のモテ期到来。
熱いまなざしをまっすぐに向けられて、
ちょっと照れてしまうワタクシです。

2015年4月14日
おおせのままに。
本日のご奉仕タイム。

2015年4月13日
業務引継ぎ。
「店番交代の時間だよ、お疲れさーん。ぺろぺろ。」
「ふにゃ~♪ それじゃ、あと、よろしくぅ。」

2015年4月12日
月刊 広告批評より(嘘)。
ほら、ライザッ◯゜...ってトコのCM、あるじゃない。
「ブーッ、ブーッ、シャラララ~」みたいな音楽の。
あれって姿勢の問題じゃないの? おなか、こうやってさ。

【てなもんやサウンド傘♪ 2015年4月12日19時半放送分】
フランスのキャピタル、花の都パリ。旅番組などでその街が紹介
されるとすれば、まず間違いなくBGMで使われる音楽のジャンル
があります。哀愁を帯びたアコーディオンの音色と、それを中心と
した少人数のアンサンブル、そして軽やかなステップを思わせる
三拍子のリズム。ミュゼットと呼ばれる、フランスの大衆音楽です。
そもそもミュゼットとは、フランスの民族楽器の名前でした。ふいご
で空気を送って演奏するパイプで、よく知られているスコットランドの
バグパイプの一種です。キャブレット、あるいはミュゼット・ド・クール
とも呼ばれています。18世紀までは庶民の楽器として広く奏でられて
いたと言われ、やがてこの楽器のための楽曲もまたミュゼットと呼ぶように
なりました。
このミュゼットという音楽が、のちにイタリアから入ってきたアコーディオンと
出会います。そして伝統的なふいごのパイプに変わって、非常に繊細な
ニュアンスを表現することが出来るアコーディオンがミュゼットの主役と
なっていったのです。19世紀末から1940年代にかけて、このスタイルの
音楽はバル(酒場)でダンス・ミュージックとして親しまれ、「バル・ミュゼット」
と呼ばれました。更には、パリでポピュラー音楽として大流行したことに
ちなんで「パリ・ミュゼット」という呼称もあります。
フランスの民族音楽にアコーディオンが採り入れられ、そこへイタリアの
節回し、そしてロマのマヌーシュ・スウィング・ジャズ(ジャンゴ・ラインハルト
などが有名)などが影響を与えつつ花開いた哀愁とエスプリの音楽、
それがミュゼットなのです。
その世界におけるアコーディオンの第一人者、ジョー・プリヴァ。
実力も人気もずば抜けていたという彼の音源を集大成した
CD3枚組が本国フランスで昨年リリースされました。そこで今夜は、
ここ日本ではあまり聴かれることのない、ジャンルとしてのミュゼットを
思いきりみなさんと堪能しました。
1、2、3はこれぞミュゼットというオーソドックスなスタイルのオリジナル曲。
まずメロディーが短調で始まり、曲の中程で一旦長調に転調して
華やかさを示し、最後は元の短調に戻って哀愁を醸す...というお約束が
盛り込まれている三拍子の楽曲たちです。
ここからは更なる進化を模索するジョー・プリヴァの世界。4はボロディン
「ダッタン人の踊り」をフィーチャーした、ご存知「ストレンジャー・イン・
パラダイス」のカバー。5は「ミュゼット楽団でロックンロールをやってみよう」
という意欲的なオリジナル曲。6はこれまたご存知プラターズの
「オンリー・ユー」のカバー、そして7はロシア民謡の定番「黒い瞳」です。
「Le Gitan Blanc - L'accordéoniste De Paris」/Jo Privat
[FREMEAUX & ASSOCIES FA5446 (仏盤・3枚組)]
オンエア曲:
1. Sa Préférée
2. Mystérieuse
3. Cauchemar
4. Stranger In Paradise
5. Rock-Accordéon
6. Only You
7. Les Yeux Noirs
Le Gitan Blanc - L'accordéoniste De Paris/Jo Privat
2015年4月11日
朝のまどろみ。
今日は遅番なので、もう少し寝るそうです。

2015年4月10日
招き猫の憂鬱。
お客さん、少ないなぁ。
雨、上がったのになぁ。
金曜日なんだけどなぁ。

【我等音楽マサイ族 2015年4月10日放送分】
Longer/Dan Fogelberg [1979年]
ダン・フォーゲルバーグはアメリカのシンガーソングライター。
スタジオミュージシャンとして腕を磨いたのち、1972年に
ファーストアルバムを発表。彼の作品はそれまでのフォーク
を基盤とした、叙情的な歌詞と美しいメロディーに定評が
あります。ギターやキーボードといった様々な楽器やコーラス
など、すべてを一人で多重録音して作り上げるスタイルは、
まさにマルチトラック録音世代の申し子と言えるでしょう。
数多くのヒット作をはじめ、一貫して完成度の高い音楽を
生み出し続けた彼ですが、2007年に56歳でその生涯を
閉じました。今日は彼の作品群の中から、1979年に発表
された「Longer」をオンエア。実にロマンチックな歌詞と、
それに似つかわしいセンシティブなメロディーとアレンジは、
聴いたあとに何とも言えない切なさと心地よさを残して
いきます。しばし余韻に浸っていたくなるような名曲です。
2015年4月 9日
伸びません。
さあ朝だ! 力を込めて! 背筋伸ばして!
・・・あれ? せ、背筋・・・、あれれ?

2015年4月 8日
箱のフタで人を挟んではいけません。
「ちっちゃいはーこ、ちっちゃいはーこ、ちっちゃい箱♪」
「おい、なんだよその歌。」

2015年4月 7日
公平にせよ。
あんた最近サバおっちゃんばっかり可愛がってるし。
あたしのコトもっとなでなでしなさいよね。ごろん。

2015年4月 6日
なんとかしなさい。
「いつ降り出すか分かったもんじゃないから、
おちおち外にも出られないぞ」とお嘆きです。
・・・そんなガン見されましても(汗)

2015年4月 5日
天気回復、もふもふ開始。
雨が上がって、ベンチも乾いて、
ようやく訪れたまったりタイム。

【てなもんやサウンド傘♪ 2015年4月5日19時半放送分】
今日から「てなもんやサウンド傘♪」は毎週日曜夜7時30分
からの放送となりました。これからも基本的なコンセプトは
そのままに、ジャンルにとらわれず様々な音楽をリスナーの
みなさんと一緒に発見して楽しんでいきたいと思っております。
今後ともお付き合いの程、なにとぞよろしくお願い申し上げます!
さて今週は放送時間の移動記念ということで、テーマを決めて
選曲する「特集形式」でお送りしました。では今回のテーマとは...、
季節のド真ん中で直球勝負、「春に関する曲」でまとめました。
ただしいくつか条件を定めまして、まず「邦楽」であること、そして
「有名だけれど最近ラジオで流れない曲(一部、こんな曲あったの!?
...というレアものも混じってますが)」の中から、まさいの気分の
おもむくままに6曲ピックアップしてお聴き頂いた次第です。
1は戦前のラジオ番組「国民歌謡」から生まれたヒット曲。世代を
超えて口ずさめる新曲を一週間にわたって放送するという番組で、
この曲を歌っている月村光子は旧姓の渡辺光子名義で1932年に
「旅は青空」をヒットさせるとともに、和田春子、渡瀬春枝、その他
多くの別名でも数々の大きなヒットを飛ばしています。両面をそれぞれ
別名で吹き込んだレコードもあるとのこと。なお彼女はのちに長らく
宝塚音楽学校にて声楽の教鞭をお執りになりました。
2は三木鶏郎の作詞作曲で、そのノリはまさに彼が戦後のラジオで
一世を風靡した冗談音楽の世界そのもの。独特の「のほほん」とした
味わいに満ちあふれています。なお、この曲は1950年4月に公開
された映画「オオ!! 細君三日天下」の主題歌となっています。
3は小柳ルミ子の7枚目のシングル曲。山上路夫作詞、森田公一
作曲によるこの作品は、前年に大ヒットした「瀬戸の花嫁」のイメージ
を踏襲した叙情的な雰囲気を持っており、この曲もまたチャートの
週間4位、年間29位を記録するヒットとなっています。
4はコーラスグループ「赤い花」で1974年にデビューし、76年にソロと
なった田山雅充の楽曲。南沙織「人恋しくて」をはじめ、多くの
アーティストへの楽曲提供でひと足早く成功していた彼が自ら放った
この「春うらら」は、チャートこそ週間16位と振るわなかったものの、
当時の多くの音楽祭において受賞曲にノミネートされるなど大いに
注目された作品で、そのシングルは実に40万枚を売り上げています。
5は「スター誕生」出身で1976年にデビューを飾った女性シンガー、
浦部雅美がその翌年に発表した2枚目のシングル曲。スタ誕
出身者の既定路線ゆえに彼女もまたアイドルとしての活躍を
期待されたのですが、自身はむしろフォーク、ニューミュージック
志向であったらしく、その意を汲んでか森田公一作曲によるこの
作品はカントリー・フォーク調の爽やかさを多分に含んでおり、
浦部雅美のぬくもりのある低音の歌声を一層引き立てています。
最後の6は、ご存知熊本県水俣市出身のシンガーソングライター、
村下孝蔵の2枚目のシングル曲。瞬くうちに彼ならではの哀愁ある
作品世界に引き込まれます。別れを象徴する季節でもある春、
その春に関する楽曲の中には、当然ながらこのように切ない別れを
テーマにした作品もまたたくさん存在するのはご承知のとおりです。
(まさいよしなり)
オンエア曲:
1. 春の唄/月村光子 (1937[昭和12]年)
2. つい春風に誘われて/ダークダックス (1950[昭和25]年)
3. 春のおとずれ/小柳ルミ子 (1973[昭和48]年)
4. 春うらら/田山雅充 (1976[昭和51]年)
5. ふるさとは春です/浦部雅美 (1977[昭和52]年)
6. 春雨/村下孝蔵 (1981[昭和56]年)
2015年4月 4日
春らしいショット、その2。
お花...散っちゃうねぇ。

2015年4月 3日
春らしいショット。
散りゆく桜、眠る猫。

【我等音楽マサイ族 2015年4月3日放送分】
春の小川/美空ひばり [1961年]
「春の小川」という歌をご存知のことと思います。これは
1912(明治45)年に発表された文部省唱歌で、当初
より作者不詳とされてきましたが、今では高野辰之作詞、
岡野貞一作曲であるというのが通説となっています。
さてこの「春の小川」、発表当初の歌詞は「春の小川は
さらさら流る、岸のすみれやれんげの花に、にほひめでたく
色うつくしく、咲けよ咲けよと、ささやく如く」(注:著作権
消滅済)という文語体で、以降3番まで歌われていました。
これが1942(昭和17)年になると歌詞に変更が加えられ、
口語体に改められるとともに3番の歌詞が削除されました。
更に1947(昭和22)年には1番の歌詞の一部が再び
改定され、現在に至っています。このようなわけで、まさに
世代を超えて誰でも知っているお馴染みの唱歌でありながら、
習った時代によって歌詞がそれぞれ異なるという状況となった
のです。なお、今でも1942年版が歌われる場合や、合唱
などの際に初出の1912年版が使用されるのは珍しいこと
ではありません。そして今朝はこの「春の小川」を、1961年に
録音された美空ひばりの貴重な音源でお聴き頂きました。
ちなみにこの録音では1942年版の歌詞が使われています。
2015年4月 2日
夏日。
束の間晴れて、午後の気温は何と27℃。
そんな中、パトロールを終えたこのお方に
ねぎらいのなでなでタイム。お疲れ様です。

2015年4月 1日
ジャパニーズ・ニンジャ。
えっ、石垣? 武者返し?
ほら...ちょろいもんですよ。